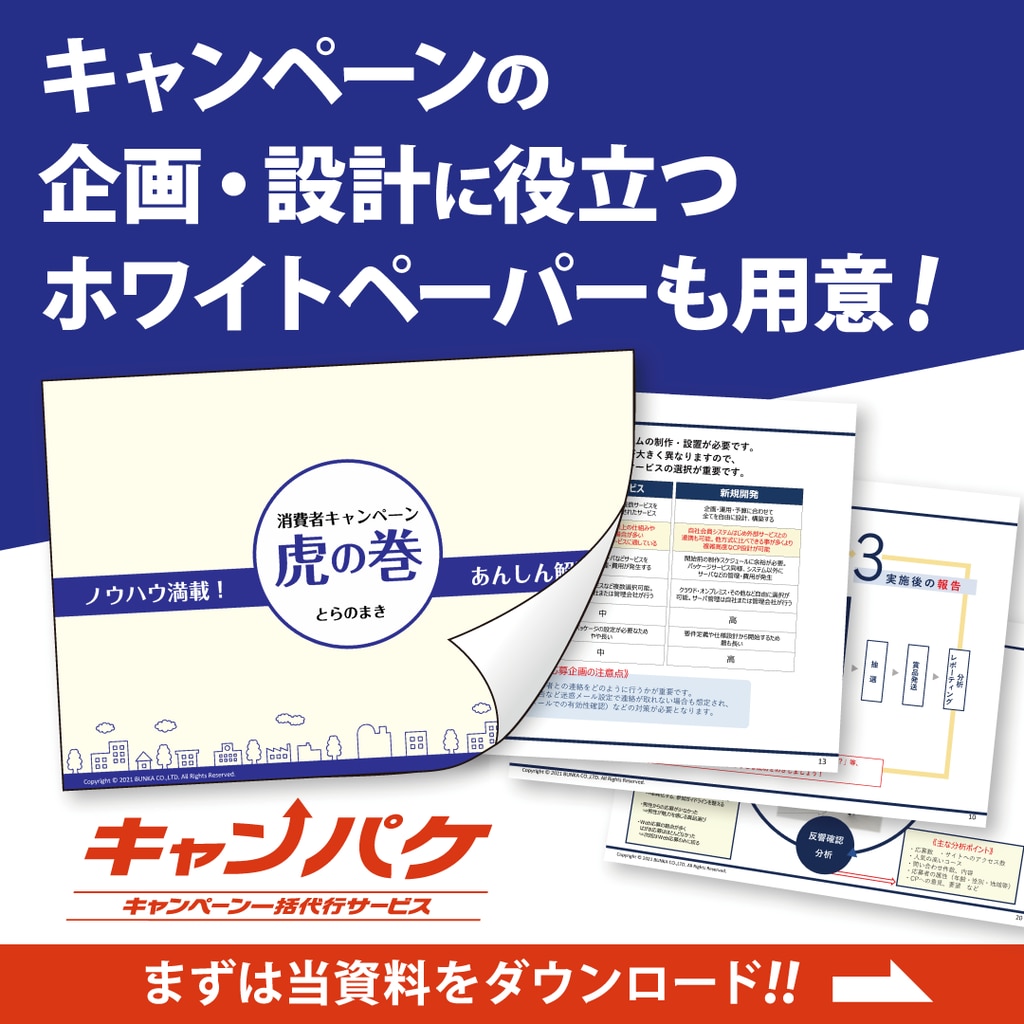キャンペーンで気を付けるべき景品表示法(景表法)のポイントを紹介!
プレゼントキャンペーンの企画・実施において、景品表示法の理解は不可欠です。
この法律を知らずにキャンペーンを行うと、意図せず法令違反となり、企業の信用を失うリスクもあります。
本記事では、景品表示法が定める景品の上限額や、キャンペーン実施時の注意点をわかりやすく解説します。
目次[非表示]
- 1.景品表示法とは?
- 1.1.景品類にあたるものとは?
- 2.景品表示法で定められた景品の種類と上限額
- 3.景品表示法違反による罰則
- 4.キャンペーン実施時の注意点
- 4.1.クローズド懸賞とオープン懸賞の違い
- 4.2.景品表示法遵守のための透明性確保
- 5.まとめ
景品表示法とは?
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者が商品やサービスを適切に選べる環境を守るための法律です。
不当な顧客誘引や誤解を招く表示を防ぎ、企業間の公正な競争を促進することを目的としています。
また、過剰な景品競争を防ぎ、商品の品質や価格に基づいた健全な市場を維持する役割も担っています。
景品類にあたるものとは?
景品表示法における「景品類」とは、顧客を誘引する目的で、事業者が商品やサービスの取引に付随して提供する経済上の利益を指します。
具体的には、商品のおまけ、懸賞の賞品、来店記念品などが含まれます。
ただし、商品やサービスの価格を直接値引くこと、通常のアフターサービス、または社会通念上商品に付属していると認められるもの(例えば、商品の説明書や保証書など)は景品類には含まれません。
キャンペーンで提供するものが景品類に該当する場合、景品表示法の規制対象となるため注意が必要です。
景品表示法で定められた景品の種類と上限額
景品表示法が規制する景品類の提供方法は、主に「総付景品」「一般懸賞」「共同懸賞」「オープン懸賞」に分けられます。
それぞれ提供できる景品の上限金額や限度額が異なります。
本記事では、総付景品、一般懸賞、共同懸賞、オープン懸賞の4種類について、それぞれの金額上限と注意点を紹介します。
総付景品
総付景品とは、商品の購入者やサービス利用者、来店者など、取引を行った全ての消費者に、懸賞やくじ引きなどの偶然性や特定の行為の優劣に関わらず提供される景品類を指します。
「ベタ付け景品」とも呼ばれ、商品やサービスの利用を条件に、もれなく提供される景品がこれに該当します。
総付景品の提供金額には上限があり、取引価額によって異なります。
※この規制は、商品やサービスを提供する事業者が、開店、創業などの記念行事に際して提供する物品は「景品類」の定義から外れる場合があるため、適用されない場合があります。
・景品類の最高金額
取引価額が1,000円未満の場合:最高額が200円まで
取引価額が1,000円以上の場合:取引価額の10分の2の金額まで
例:商品購入者対象のもれなくもらえるプレゼントキャンペーン
3,000円の商品を購入した際に提供できる総付景品の金額上限は、3,000円の10分の2となるため、600円までとなります。
一般懸賞
一般懸賞とは、商品やサービスの購入者、利用者に対して、くじ引きや抽選といった偶然性、またはクイズやゲームの正誤、作品の優劣などによって景品類を提供するものです。
「クローズド懸賞」とも呼ばれており、特定の条件を満たした応募者の中から抽選で当選者を決定し、景品を提供する場合がこれに該当します。
一般懸賞で提供できる景品には、以下のように景品類の最高金額と総額にそれぞれ限度額が定められています。
・景品類の最高金額
取引価額が5,000円未満の場合:取引価額の20倍まで
取引価額が5,000円以上の場合:一律10万円まで
景品類の総額:懸賞に係る売上予定総額の2%以内
例:商品購入者対象の抽選キャンペーン
3,000円の商品購入者を対象とした抽選キャンペーンの場合、景品類の最高額は3,000円の20倍となるため、6万円以下である必要があります。
また、キャンペーン全体の景品総額は、対象商品の売上予定総額の2%以内におさめる必要があります。
共同懸賞
共同懸賞は、一定の地域や業界の複数の事業者が共同して行う懸賞です。
例えば、一定の地域(市町村等)の小売業者やサービス業者の相当多数が共同で実施する懸賞や商店街などが中元・歳末セールなどで実施する懸賞等がこれに該当します。
・景品類の最高金額
取引価額にかかわらず30万円まで
景品類の総額: 懸賞に係る売上予定総額の3%以内
オープン懸賞
オープン懸賞は、商品やサービスの購入、来店などを応募条件としない懸賞です。
例えば、クイズ回答やSNSでのフォロー&リポストなどで誰でも応募できる形式がこれに該当します。
オープン懸賞は景品表示法上の「景品類」に該当しないため、原則として金額の上限規制はありません。
ただし、あまりに高額な景品は景品表示法の趣旨に反すると判断される可能性があるため、金額設定には留意が必要です。
景品表示法違反による罰則
景品表示法に違反した場合、行政指導や措置命令の対象となり、それに従わない場合は2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
法人の業務に関連する違反行為であった場合、法人自体にも3億円以下の罰金が科されることもあります。
さらに、2024年10月には不当表示(優良誤認表示・有利誤認表示)に対する直接的な刑事罰(100万円以下の罰金)を科す直罰規定が新設されるなど、違反行為に対する規制は強化される傾向にあります。
法令違反は企業の社会的信用の失墜やブランドイメージの低下にもつながるため、景品表示法のルールを正しく理解し遵守することが極めて重要です。
キャンペーン実施時の注意点
キャンペーンを成功させるためには、景品表示法のルールを遵守することが不可欠です。
特に景品の金額設定や、キャンペーンの期間、応募条件、告知方法など、細部にわたる注意が必要です。
クローズド懸賞とオープン懸賞の違い
キャンペーン企画において、クローズド懸賞とオープン懸賞のどちらの形式を採用するかは重要な決定事項です。
キャンペーンの目的やターゲット層、予算に応じて、適切な懸賞形式を選択し、それぞれの条件に基づいた企画設計を行いましょう。
・クローズド懸賞
商品の購入やサービスの利用、来店など、特定の取引を行った消費者のみが応募できる懸賞です。
取引に付随するため、景品表示法による景品類の金額規制の対象となります。
・オープン懸賞
商品購入やサービス利用といった条件がなく、誰でも応募できる懸賞です。
取引に付随しないため、景品表示法上の景品類には該当せず、原則として金額の上限規制はありません。
景品表示法遵守のための透明性確保
景品表示法を遵守し、消費者からの信頼を得るためには、キャンペーンにおける透明性の確保が非常に重要です。
特に抽選による懸賞の場合、その抽選方法や当選者数の告知などが曖昧であったり、実際の内容と異なったりすると、消費者に不信感を与え、景品表示法違反となる可能性があります。
キャンペーン規約などで抽選方法を明確に告知したり、景品の内容や当選者数を正確に表示したりすることが、透明性を確保し、消費者からの信頼を得る上で不可欠です。
また、問い合わせ窓口を設置するなど、消費者が疑問点を解消できる体制を整えることも、トラブル防止につながります。
まとめ
プレゼントキャンペーンは、ブランド認知度向上や顧客エンゲージメント強化に非常に有効なマーケティング手法です。
しかし、その成功の鍵は、単に魅力的な景品を用意することだけではありません。
景品表示法を正しく理解し遵守することこそが、消費者に安心感を与え、健全で信頼性の高いキャンペーンを展開するための鍵です。
これにより、キャンペーンの効果を最大化し、顧客との長期的な関係を築く強固な基盤となるでしょう。