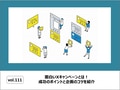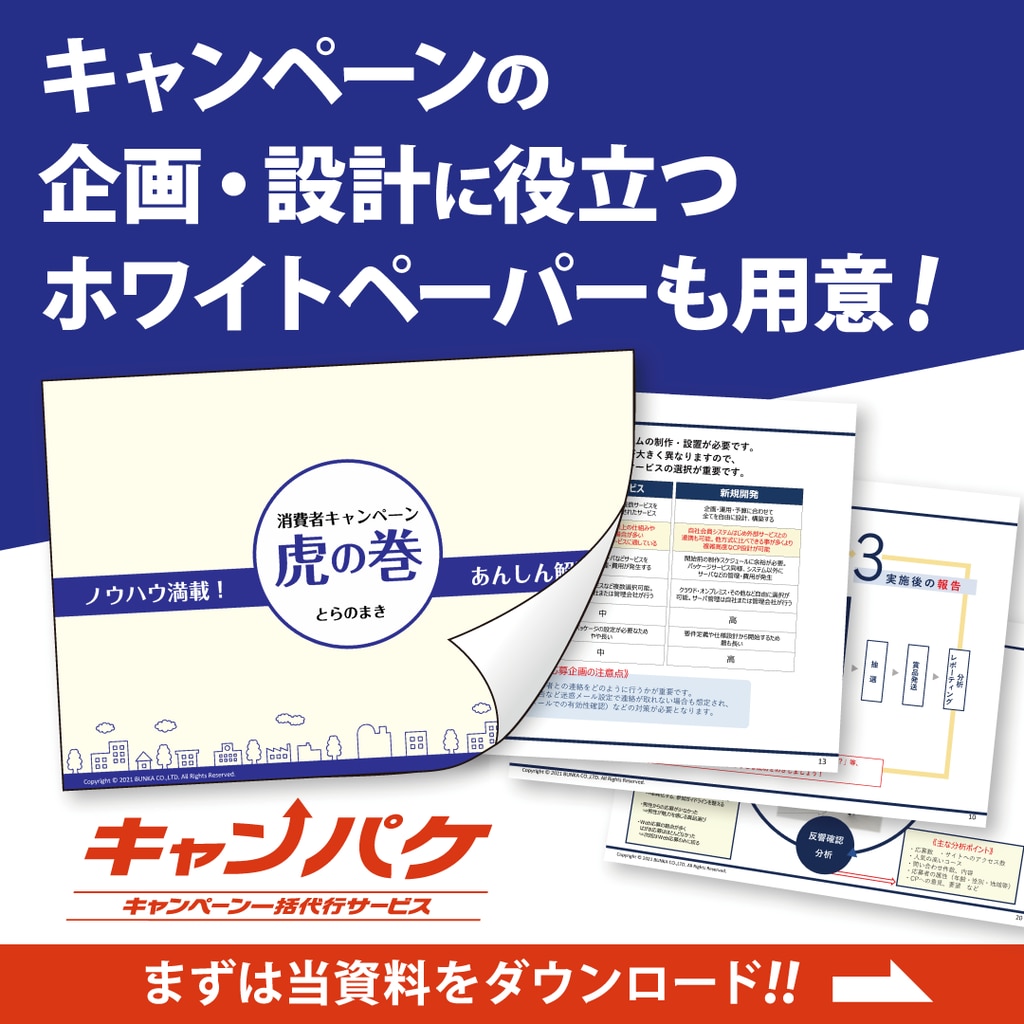マストバイキャンペーン成功の鍵!企画のポイントから応募方法、事例を紹介
マストバイキャンペーンは、商品の購入を応募条件とする販売促進手法であり、消費者の購買意欲を直接的に刺激し、売上向上に大きく貢献します。
この仕組みにより、企業は販売促進だけでなく、新規顧客の獲得や既存顧客のロイヤルティ向上も同時に期待できます。
本記事では、マストバイキャンペーンの基礎知識から、成功のポイント、実際の事例までを解説します。
マストバイキャンペーンとは?商品購入を促す販売促進の手法
マストバイキャンペーンとは、特定の商品やサービスの購入者のみが参加できる賞品付きのプロモーション活動を意味します。
購入証明としてレシートや商品パッケージの一部などを提示する必要があるため、非購入者は応募できません。
この仕組みにより、キャンペーンへの参加が直接的な購買動機となり、売上向上に繋がりやすいのが大きな特徴です。
企業にとっては、販売促進だけでなく、新規顧客の獲得や既存顧客のロイヤルティ向上といった効果も期待できる重要なマーケティング手法の一つです。
企業がマストバイキャンペーンを実施する3つの目的
企業がマストバイキャンペーンを実施する目的は多岐にわたりますが、主に「売上向上」「新規顧客の獲得」「既存顧客との関係強化」の3つが挙げられます。
これらの目的は相互に関連しており、キャンペーンを戦略的に設計することで、複数のメリットを同時に享受することが可能です。
単なる値引きとは異なり、ブランドイメージを損なうことなく購買を促進できるため、多くの企業にとって有効な販売促進策として活用されています。
1、売上向上
マストバイキャンペーンの最も直接的な目的は、商品の販売を促進し、短期的な売上を向上させることです。
魅力的な賞品を用意することで、消費者の「この商品を買って応募したい」という意欲を刺激し、購入の強力な後押しとなります。
特に、応募条件を「対象商品を2点以上購入」のように設定すれば、顧客一人あたりの購入単価を引き上げる効果も期待できます。
また、キャンペーン期間中は店頭での露出が増え、消費者の目に留まりやすくなるため、普段はその商品を選ばない層へ購入を促すきっかけにもなります。
2、新規顧客の獲得
マストバイキャンペーンは、まだ自社の商品やブランドを知らない、あるいは利用したことのない新規顧客を獲得するための有効な手段です。
話題性のある賞品や人気キャラクターとのコラボレーション企画などを実施することで、これまでブランドに関心のなかった層にも情報を届けることができます。
キャンペーンをきっかけに初めて商品を購入した顧客が、その品質や価値を実感すれば、リピート購入に繋がる可能性が生まれます。
このように、キャンペーンは新規顧客との最初の接点を作り出すというメリットがあり、中長期的な顧客基盤の拡大に貢献します。
3、既存顧客との関係強化
マストバイキャンペーンは、既に商品を購入してくれている既存顧客への感謝を伝えるとともに、ブランドとの関係性をより深めるための施策としても機能します。
購入者限定の特別な企画を用意することで、顧客は「選ばれた」「大切にされている」という特別感を感じ、ブランドへの愛着やロイヤルティが高まります。
定期的にキャンペーンを実施することで、顧客の継続的な購入を促し、ファン化を促進するメリットがあります。
優良顧客との長期的な関係構築は、安定した事業成長の基盤となるため、既存顧客の満足度を高めることは非常に重要です。
マストバイキャンペーンで使われる代表的な4つの応募方法
マストバイキャンペーンの応募方法は、大きく分けてアナログな手法とデジタルな手法があります。
近年ではスマートフォンの普及に伴い、手軽なデジタル応募が主流になりつつあります。
一方で、ハガキを使った応募方法も根強く残っています。
それぞれの方法にはメリット・デメリットがあり、ターゲット層の属性やキャンペーンの目的に合わせて最適な手法を選択することが、参加しやすさを高め、応募数を増やす上で重要になります。
1、レシートを撮影して応募する
購入レシートをスマートフォンで撮影し、キャンペーンサイトやLINE公式アカウントを経由し、画像をアップロードして応募する方法は、近年最も主流となっている手法です。
参加者はハガキを用意したり切手を貼ったりする手間がなく、購入後すぐにその場で手軽に応募できるのが大きなメリットです。
また、特定の商品だけでなく、店舗での合計購入金額を条件にするなど、キャンペーン設計も自由に設定できます。
2、シリアルナンバーを入力して応募する
商品パッケージやシールに印字されたシリアルナンバーを、キャンペーンサイトで入力して応募する方法です。
この方式は、購入した商品一つ一つにユニークな番号が付与されているため、不正応募を防ぎやすいというメリットがあります。
また、シリアルナンバーを入力した直後に当落が分かる「インスタントウィン形式」との相性が非常に良く、参加者の期待感を高めることができます。
ユーザーはレシートを撮影したり、個人情報を毎回入力したりする手間が省けるため、手軽さに応募できることで、応募率の向上が期待できます。
特に、デジタルコンテンツやポイントなどを賞品とする場合に適した手法です。
3、商品に付いている応募シールを集めて応募する
商品に貼付される応募シールや応募券を規定枚数集め、専用の応募ハガキや市販のハガキに貼って郵送する方法は、古くからある代表的な手法です。
複数の商品を購入する必要があるため、キャンペーン期間中の継続的な売上貢献や、顧客単価の上昇に繋がりやすいという特徴があります。
シールを集める過程でコレクション的な楽しさが生まれ、参加者の没入感を高める効果も期待できます。
4、パッケージのバーコードなどを切り取って応募する
商品パッケージに印刷されているバーコードや応募マークを切り取り、ハガキに貼って応募する方法です。
応募シール方式と同様に、複数商品の購入を促す効果が期待できる古典的な手法です。
実際に商品を消費しなければ応募マークを切り取れないため、不正な応募が起こりにくいというメリットがあります。
3、4の手法はハガキの用意や郵送といった手間がかかるため、他の方法に比べて参加のハードルが高く、応募率が伸び悩む傾向も見られます。
そのため、応募率を高めるには、手間をかけてでも応募したいと思わせるような、魅力的な賞品設計が不可欠です。
マストバイキャンペーンを成功に導くためのポイント
マストバイキャンペーンの効果を最大化し、成功に導くためには、事前の計画と戦略的なアプローチが不可欠です。
魅力的な賞品を企画することはもちろん、参加のしやすさを考慮した設計、SNSや店頭での効果的な告知、そして参加者が安心して応募できる透明性の確保が重要となります。
これらのポイントを総合的に押さえることで、キャンペーンの参加者数を増やし、最終的な目標達成に繋げることができます。
【ターゲットが魅力を感じる賞品を企画する】
キャンペーンの成否を大きく左右するのが賞品の魅力です。
ターゲット層が「欲しい」と強く感じるものでなければ、購入してまで応募しようという動機付けにはなりません。
まずは、自社の商品を購入する顧客層の年齢、性別、ライフスタイル、興味関心を深く分析することが重要です。
その上で、キャンペーンでしか手に入らないオリジナルグッズ、特別なイベントへの招待など、ターゲットの心に響く賞品を企画する必要があります。
賞品の選定が、キャンペーン全体の成果に直結すると言っても過言ではありません。
【参加のハードルが低いキャンペーンを設計する】
どれだけ魅力的な賞品を用意しても、応募方法が複雑で面倒だと参加者は途中で離脱してしまいます。
応募率を高めるためには、参加のハードルをできるだけ低く設定することが肝心です。
例えば、スマートフォンでレシートを撮影するだけで応募が完了する仕組みや、応募フォームの入力項目を最小限に抑えるといった工夫が有効です。
また、応募条件となる購入金額や購入点数を高く設定しすぎると、参加できる人が限られてしまいます。
ターゲット層の購買行動を考慮し、無理なく参加できる条件を設定することで、より多くの応募者を集めることができます。
【キャンペーンの認知度を高める】
キャンペーンを多くの人に知ってもらうためには、SNSでの情報拡散と店頭での直接的なアピールの両方を活用することが重要です。
・SNSで広く拡散する
XやInstagram、LINEなどのSNSは、情報を瞬時に多くの人に届けることができる強力なツールです。公式アカウントで情報を発信するだけでなく、特定のハッシュタグをつけた投稿を参加条件にしたり、インフルエンサーに協力を依頼したりすることで、参加者やフォロワーによる自発的な拡散を促し、より多くの潜在顧客にアプローチできます。
・店頭で直接アピールする
消費者が実際に商品を購入する店頭は、キャンペーン告知の重要な場所です。
商品棚のPOPやポスター、のぼりなどを活用して来店客の注意を引きつけたり、商品パッケージに直接キャンペーン情報を記載したりすることで、その場での「ついで買い」や「衝動買い」を促し、キャンペーンへの参加を後押しできます。
オンラインとオフラインの両方でアプローチすることで、より幅広い層にキャンペーンの存在を知らせ、集客効果を最大化できるでしょう。
【応募から当選までの流れを明確に提示する】
参加者が安心してキャンペーンに参加できるよう、応募規約やフローを分かりやすく提示することが重要です。
応募方法、応募期間、当選者の発表方法、賞品の発送時期といった一連の流れをキャンペーンサイトなどに明記し、参加者の疑問や不安を解消する必要があります。
特に、個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーを明確に示すことは、企業の信頼性を高め、応募率の向上に繋がります。
問い合わせ窓口を設置し、質問に迅速に対応できる体制を整えておくことも、スムーズなキャンペーン運営には欠かせません。
実施前に必ず確認すべきマストバイキャンペーンの注意点
マストバイキャンペーンを計画する際には、その効果や魅力だけでなく、法的な規制や潜在的なリスクにも注意を払う必要があります。
特に、賞品の価格設定に関する景品表示法の遵守は絶対条件です。
また、デジタル応募が主流になる中で、レシートの使い回しなどの不正応募への対策も欠かせません。
これらの注意点を事前に把握し、適切な対策を講じることで、トラブルを防ぎ、公正で安全なキャンペーン運営を実現できます。
景品表示法で定められた賞品の上限額を守る
マストバイキャンペーンは、景品表示法における「懸賞」に該当するため、提供できる賞品の金額に上限が定められています。
キャンペーンを企画する際は、必ず景品表示法の内容を確認し、定められた金額の範囲内で賞品を設計する必要があります。
【キャンペーンで気を付けるべき景品表示法(景表法)のポイントを紹介!】
https://www.campake.com/blog/212
不正な応募を防ぐための対策を立てる
キャンペーンの公平性を保ち、想定外のコスト発生を防ぐためには、不正応募への対策が不可欠です。
特にレシート応募では、同じレシートの使い回しや、画像加工による応募日付・購入金額の改ざんといった不正が起こり得ます。
対策としては、応募時にレシートへ手書きで印を付けてもらう、シリアルナンバーを活用して応募を一人一回に限定するなどの方法が有効です。
また、応募規約に不正が発覚した場合は当選を無効にする旨を明記しておくことも重要です。
【事例から学ぶ】マストバイキャンペーンの成功例
マストバイキャンペーンを成功させるには、他社の成功事例から学ぶことが有効です。
ここでは、SNSとの連動で話題性を生んだ事例や、デジタル賞品を活用して参加のハードルを下げた成功事例を紹介します。
SNS連動企画で話題性を生んだ食品メーカーのケース
ある食品メーカーは、自社商品の購入者を対象としたマストバイキャンペーンにおいて、SNSとの連動を効果的に活用しました。
応募条件として、購入した商品を使ったアレンジレシピの写真を、指定のハッシュタグと共にInstagramへ投稿することを設定しました。
この企画により、参加者が自身のSNSアカウントでキャンペーン情報を自然な形で拡散する流れが生まれました。
結果として、広告費をかけずに幅広い層へリーチできただけでなく、ユーザーが作成した多様なコンテンツ(UGC)が集まり、商品の新たな魅力を伝えることにも成した、優れた成功事例と言えます。
※UGCは「User Generated Content」の略で、日本語では「ユーザー生成コンテンツ」と訳されます。これは、企業やメディアではなく、一般のユーザーによって制作・発信されたコンテンツ全般を指します。
デジタル賞品で参加しやすさを高めた飲料メーカーのケース
ある飲料メーカーでは、若年層をターゲットにしたマストバイキャンペーンで、賞品をデジタルギフトに特化させることで成功を収めました。
対象商品に付いているシリアルナンバーをキャンペーンサイトで入力すると、その場でLINEポイントや各種キャッシュレス決済で使えるポイントが当たる仕組みです。
応募から賞品受け取りまでがスマートフォン一つで完結する手軽さと、すぐに結果が分かる即時性にあります。
物理的な賞品の発送にかかるコストや手間を削減できるという企業側のメリットも大きく、参加しやすさを追求した企画として参考にできます。
まとめ
マストバイキャンペーンとは、商品の購入を条件とすることで、直接的な売上向上を目指す販売促進手法です。
その目的は売上アップに留まらず、新規顧客の獲得や既存顧客との関係強化にも及びます。
キャンペーンを成功させるには、ターゲットに響く賞品の企画、SNSなどを活用した効果的な告知、そして参加しやすい応募フローの設計が鍵となります。
また、実施にあたっては景品表示法などの法律を遵守し、不正対策を講じることも不可欠です。
これらのポイントを踏まえて戦略的に企画・実行することで、その効果を最大限に引き出すことができます。